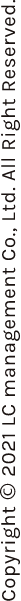GLOSSARY
用語集
あ行
RC造
あーるしーぞう
「Reinforced Concrete(鉄筋コンクリート)」の略で、鉄筋を入れて補強されたコンクリート構造のこと。木造や鉄骨造と比較して耐火性・遮音性・耐震性に優れており、マンションや中高層の賃貸物件に多く用いられる。一方で建築コストは高めだが、長期的には修繕頻度が抑えられ、資産価値の維持にも寄与する。
IHクッキングヒーター
あいえいちくっきんぐひーたー
電磁誘導加熱(Induction Heating)を利用して調理を行う加熱機器。表面がフラットで掃除がしやすく、火を使わないため安全性が高い。単身用物件では一口~二口タイプ、ファミリー物件では二口~三口タイプが一般的。
青色申告
あおいろしんこく
賃貸不動産を経営している個人(大家)や法人が、税務署に「青色申告承認申請書」を提出することで利用できる確定申告制度。複式簿記で帳簿を記帳し、貸借対照表や損益計算書を作成・提出する必要があるが、最大65万円の特別控除が受けられるなどの税制上のメリットがある。赤字が出た場合は、翌年以降に繰り越すこともできるため、収益が安定しない初期の不動産運用では特に有利。
委託管理
いたくかんり
物件の所有者(オーナー)が、建物や入居者の管理業務を専門の不動産管理会社に委託すること。委託内容には、入居者募集、契約締結、家賃集金、クレーム対応、退去精算、原状回復の手配など多岐にわたる。委託形態には「一括借上(サブリース)」と「管理委託契約(通常管理)」があり、リスクや報酬体系が異なる。
一棟管理
いっとうかんり
賃貸アパートやマンション1棟を丸ごと管理対象とする形態。共用部の維持管理(清掃・電球交換・定期点検など)や建物全体の設備管理(消防設備、給水ポンプ、エレベーターなど)も含まれる。戸単位の管理(区分管理)よりも包括的な対応が求められる。特に入居率の維持や建物の資産価値保全の面で、管理会社の力量が問われる分野。
違約金
いやくきん
契約期間中に借主が正当な理由なく解約する場合など、契約違反に対して課される金銭的なペナルティ。具体的には、1年未満での解約で1ヶ月分の賃料を違約金とするケースが一般的。契約書に明記されていることが前提となる。過度な違約金は「消費者契約法」により無効とされる場合もあるため、管理会社側も注意が必要。
SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)
えすあーるしーぞう
SRC造とは、「Steel Reinforced Concrete」の略で、日本語では「鉄骨鉄筋コンクリート造」と訳される構造方式です。鉄骨の骨組みに鉄筋を組み、さらにその外側をコンクリートで覆うことで、鉄骨の強度とコンクリートの耐火性・耐久性を併せ持つ堅牢な建築構造です。
S造(鉄骨造)
えすぞう
柱や梁などの骨組みに鉄骨(鋼材)を用いた構造の建物。木造よりも耐震性・耐久性に優れ、RC造よりもコストは抑えられる。アパートや店舗併用住宅に多く、軽量鉄骨と重量鉄骨に分かれる。鉄の腐食や火災対策として、防錆・耐火処理が重要。
追い焚き
おいだき
一度ためた浴槽のお湯を再度加熱する機能。ファミリー向け物件や長時間お風呂を楽しむ層に人気の設備で、ガス給湯器やエコキュートなどで対応可能。追い焚き機能付き給湯器の設置にはコストがかかるが、入居者の満足度向上と空室対策に効果があるため、導入を検討するオーナーも多い。
か行
解約予告
かいやくよこく
入居者が退去する場合に、契約書で定められた期間前に通知する義務のこと。一般的には「1ヶ月~2ヶ月前までに通知」が多い。退去日までに原状回復や清掃などの手配を行うためにも、管理会社やオーナーにとって重要なプロセス。予告期間内の家賃は発生するため、入居者側もスケジューリングが必要となる。
管理会社
かんりがいしゃ
オーナーに代わり、賃貸物件の運営・管理を行う専門会社。主な業務内容には、入居者募集、契約業務、家賃回収、クレーム対応、設備点検、退去後の原状回復工事などがある。対応力や顧客満足度が入居継続率に大きく影響するため、オーナーにとって信頼できる管理会社の選定は極めて重要。報酬体系には「定率管理」「定額管理」がある。
管理費
かんりひ
建物の共用部分(廊下・エントランス・ゴミ置き場など)の維持管理や、清掃・点検・光熱費などに充てられる費用。入居者が毎月家賃とともに支払う。マンションやアパートでは家賃とは別に設定されることが多く、見かけ上の家賃が安く感じられることもある。管理費の使途は明確にすることがトラブル防止につながる。
給湯器
きゅうとうき
水を温めて給湯する装置。主にガス・電気・灯油を熱源とし、戸建や集合住宅の風呂・洗面・キッチンに給湯を行う。代表的な種類には**瞬間湯沸かし式・貯湯式・エコジョーズ(高効率型)**などがある。
原状回復
げんじょうかいふく
退去時に、入居者が部屋を入居時の状態に戻すことを原則とする考え方。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、「通常損耗(経年劣化)」と「借主の故意・過失による損傷」を明確に区別することが推奨されている。クロスの汚れや破損、床の傷などは判断が分かれるポイントであり、契約時の説明と写真記録が重要。
更新事務手数料
こうしんじむてすうりょう
賃貸借契約を更新する際、管理会社が借主から徴収する手数料。通常は家賃の0.5〜1ヶ月分が相場。更新料とは別に請求されることがあり、契約書に明記されている必要がある。更新に関する事務処理(書類作成、契約締結、更新内容説明など)に対して課される。
更新料
こうしんりょう
賃貸契約を継続する際に、借主が貸主へ支払う一時金。関東地方では1〜2ヶ月分の家賃が相場だが、全国的に見れば設定しない地域もある。更新料は契約自由の原則に基づき設定されるが、その説明責任は管理会社やオーナーにある。更新時には「契約更新料」「更新事務手数料」などが別々に請求されることも。
公正証書
こうせいしょうしょ
公証人役場で作成される法的効力の高い文書。賃貸借契約においては、家賃滞納や明渡請求に関する条項を含めることで、裁判を経ずに強制執行が可能になる(「執行認諾文言付き公正証書」)。高額物件や法人契約など、トラブルが想定される契約で利用されるケースがある。作成には費用と時間がかかるが、抑止効果は高い。
固定資産税
こていしさんぜい
土地・建物などの不動産を所有している者に課される地方税。毎年1月1日時点の所有者に対して課税され、市町村から納税通知書が送付される。建物の構造や築年数、土地の評価額に応じて算出され、賃貸経営における固定支出として重くのしかかる。長期経営では、減価償却とのバランスを取った資金計画が必要。
さ行
差押え
さしおさえ
家賃滞納などにより、貸主が法的手続きを通じて借主の財産(給与、預貯金、動産など)を押さえる強制執行手段の一つ。通常は訴訟を経て勝訴判決や債務名義を取得後に行われる。賃貸管理では、保証会社が代位弁済した後に借主に対して差押えを行うケースもある。公正証書の活用で裁判手続を省略できることがある。
サブリース
さぶりーす
オーナーから賃貸物件を一括で借り上げ、不動産会社が第三者に転貸(また貸し)する契約形態。サブリース会社が空室リスクや入居者対応を担うが、オーナーには一定の賃料が保証されるため「家賃保証」などと呼ばれることも多い。ただし、契約によっては数年後に家賃が減額される「家賃見直し条項」や、解約条件に不利な内容が含まれることもあり、トラブルも多発している。契約内容の精査が極めて重要。
敷金
しききん
借主が入居時に貸主へ預ける保証金。契約終了時に、未払いの家賃や修繕費用などを差し引いたうえで返還される。法律上は「預り金」であり、原則として返金義務があるが、原状回復費用をめぐるトラブルの原因になりやすい。敷金ゼロ(ゼロゼロ物件)を選ぶ入居者も多いが、その分、退去時に多額の請求を受けるケースもある。
敷引
しきびき
関西地方を中心に見られる慣習で、入居時に支払った敷金のうち、契約終了後でも返還されない部分をあらかじめ定めておく方式。たとえば「敷金20万円、敷引10万円」と記載されていれば、退去時に10万円が償却され、残額10万円が返金される。契約書に明記されていない敷引は無効とされる可能性があるため、事前の確認が重要。
事故物件
じこぶっけん
過去に自殺・他殺・孤独死・火災など、人の死亡に関わる事件・事故があった物件。入居者の心理的抵抗感が強く、家賃が相場より大幅に下げられることが多い。貸主・仲介業者には「告知義務」があり、事実を知りながら説明しなかった場合には損害賠償の対象となる可能性がある。告知の期間や範囲については明確な法律規定はなく、近年ガイドラインが整備されつつある。
自主管理
じしゅかんり
オーナー自らが入居者募集、契約手続き、家賃回収、クレーム対応など、すべての管理業務を行う運用方法。管理委託費がかからずコストを抑えられるメリットがあるが、専門知識や対応力、時間的余裕が求められるため、トラブルが発生した際の対応が遅れるリスクもある。副業的に不動産経営を行う個人オーナーには負担が大きい。
重要事項説明書
じゅうようじこうせつめいしょ
宅地建物取引士が借主に対し、物件の契約に関する重要な事項を記載・説明する法定書面。所在地・契約期間・解約条件・敷金・更新料・設備の有無などが明記されている。説明は宅建士が対面またはIT重説(オンライン)で行い、署名捺印をもって契約締結に進む。後々のトラブル回避のためにも、十分な理解と確認が必要。
譲渡
じょうと
契約上の地位や物件そのものの権利を他者に移すこと。賃借権の譲渡は原則として貸主の承諾が必要で、無断で行った場合、契約違反となる可能性がある。不動産の売却により所有者が変更された場合でも、借主の契約は原則として継続される(借地借家法による保護)。
た行
退去精算
たいきょせいさん
退去後、原状回復費用、クリーニング費用、未払い家賃・光熱費などの清算を行うこと。敷金から差し引いたうえで、精算書を作成し入居者へ通知・返金を行う。費用の明細や根拠が不明確だとトラブルになるため、見積書や写真を添付するのが望ましい。国交省ガイドラインに沿った対応が求められる。
退去立会い
たいきょたちあい
入居者が退去する際に、管理会社やオーナーが現地で部屋の状態を確認する作業。壁紙の汚れ、床のキズ、設備の破損などをチェックし、原状回復費用の負担割合を判断する。入居者と同席して行うことで、後のトラブルを避けやすくなる。記録用の写真撮影とチェックリスト作成が重要。
滞納保証
たいのうほしょう
入居者が家賃を滞納した際に、保証会社が代わりにオーナーへ家賃を立て替えて支払う仕組み。家賃保証会社が審査・契約を行い、入居者が保証料を支払う。保証内容には「滞納家賃のみ」か「原状回復費用・訴訟費用まで含む」かなど種類がある。オーナーにとってはリスク軽減の重要な手段。
ダクト
だくと
換気・排気・空調などのために空気を通す管。天井裏や壁内に隠れて設置されることが多い。キッチンのレンジフードや浴室換気扇などに接続され、室内の空気を外部に排出する。
宅配ボックス
たくはいぼっくす
不在時でも宅配物を受け取れるようにするための設備で、集合住宅の共用部に設置されることが多い。入居者が専用キーや暗証番号で荷物を取り出す仕組み。近年はスマートロック・QRコード・クラウド管理型などのハイテク化も進んでいる。
W造(木造)
だぶりゅーぞう
W造は「Wooden construction」の略で、木材を主構造とする建築方式です。日本の伝統的な在来工法をはじめ、近年ではツーバイフォー(2×4)工法なども多く採用されています。賃貸市場においては、アパートや戸建て住宅を中心に最も普及している構造形式です。
仲介手数料
ちゅうかいてすうりょう
不動産仲介業者が契約の成立に際して、貸主・借主から受け取る報酬。法律上、借主・貸主のいずれかから「家賃の1ヶ月分(税込1.1ヶ月分)以内」が上限とされている。借主負担が慣習だが、双方から折半(0.5ヶ月ずつ)するケースもある。事前に説明と同意が必要。
長期修繕計画
ちょうきしゅうぜんけいかく
建物の外壁・屋上・設備機器などの大規模修繕を、将来にわたり計画的に実施するためのスケジュールと予算の見通しをまとめたもの。建物寿命や資産価値を維持するために不可欠。通常は25〜30年のスパンで作成される。
定期借家契約
ていきしゃくやけいやく
契約期間満了時に、貸主が通知すれば契約が終了する借家契約。再契約の手続きが必要で、自動更新はされない。オーナーが物件を将来的に自用する予定がある場合や、一定期間のみの賃貸を想定している場合に活用される。契約時には「定期借家契約であることの書面による明示」が義務づけられている。
点検報告書
てんけんほうこくしょ
建物や設備の点検を実施した結果を記録・報告する書類。消防設備・エレベーター・貯水槽など法定点検に付随して作成されることが多く、所管行政への提出義務がある。不備の指摘事項がある場合は速やかな是正が求められる。
電子契約
でんしけいやく
従来の紙と印鑑による契約に代わり、電子署名とデジタルデータを用いて行われる契約方式。クラウドサインやDocuSignなどの電子契約サービスを使い、契約手続きのスピードアップ・印紙税の不要・非対面対応が可能となる。2022年の宅建業法改正により、賃貸借契約にも電子契約が全面解禁された。
な行
内見
ないけん
入居希望者が、実際の賃貸物件を見学すること。間取り・設備・周辺環境を確認できる重要なプロセス。内見の際は、物件の清掃状況、日当たり、騒音、共用部の管理状態などもチェックポイントとなる。管理会社や仲介業者が同行することが多く、鍵の手配や事前予約が必要なケースもある。第一印象が入居判断に大きく影響するため、管理側としても対応品質が問われる場面。
内容証明郵便
ないようしょうめいゆうびん
文書の「内容」「差出日」「差出人・受取人」が日本郵便により証明される郵便手段。家賃滞納者への督促や契約解除通知、敷金返還請求、原状回復に関する異議申立てなど、法的トラブルの前段階でよく使用される。内容証明自体に法的強制力はないが、証拠能力が高く、交渉・訴訟時に有効。
入居審査
にゅうきょしんさ
賃貸物件への入居希望者に対し、オーナーまたは管理会社・保証会社が行う評価・判断プロセス。審査内容は、収入状況、勤務先、緊急連絡先、保証人の有無、過去の滞納歴など。滞納リスクを最小限に抑えるため、保証会社による審査が一般的。場合によっては、審査落ちの理由は非開示とされる。審査基準は各社で異なり、物件や家賃額に応じた柔軟な判断が必要。
入居率
にゅうきょりつ
管理物件の総戸数に対して、現在入居中の戸数の割合を示す指標。
計算式:
「入居中戸数 ÷ 総戸数 × 100(%)」
入居率が高いほど安定した収益が期待できるため、物件の経営指標として最重要。逆に、空室が多いと管理会社の営業力や物件の競争力が疑われる要素にもなる。
抜け番
ぬけばん
集合住宅で「4号室」や「9号室」など、縁起を気にして一部の部屋番号を意図的に設定しないこと。事故物件や退去が続いた部屋を欠番にするケースもある。管理上は記録ミスを防ぐため、台帳上の管理番号とずれがないよう注意が必要。
年間収支報告書
ねんかんしゅうしほうこくしょ
1年間の賃貸経営における収入・支出をまとめた書類。家賃収入、管理費、修繕費、固定資産税、保険料などを記載し、オーナーへ定期的に報告する。確定申告の資料として活用されることが多く、税務署からの問い合わせにも対応できるよう正確な作成が求められる。クラウド管理ソフトなどを用いて自動作成されるケースも増えている。
は行
ハザードマップ
はざーどまっぷ
自然災害による被害の想定区域を地図上に示したもの。地震、津波、洪水、土砂災害などのリスクが可視化されており、不動産取引時の説明が義務化されている(2020年の法改正により)。ハザードマップ上のリスクに応じて、保険加入条件や入居者の判断に影響を与えるため、正確な説明が必要。
バルコニー・ベランダ
ばるこにーべらんだ
建物の外壁から張り出した屋外スペース。バルコニーは基本的に屋根なし、ベランダは屋根付きが一般的な違い。ただし実務上は混用されることも多い。共用部分に該当するケースが多く、勝手に物置・エアコン室外機・喫煙場所とすることは禁止される場合もある。消防法上、避難経路としての機能も持つ。
PC造(プレキャストコンクリート造)
ぴーしーぞう
PC造は「Precast Concrete construction」の略で、あらかじめ工場で製造された鉄筋コンクリート部材(パネル)を現場で組み立てて建築する方式です。精度の高いパネルを用いるため、工期が短く、品質のばらつきが少ないという特徴があります。
表面利回り
ひょうめんりまわり
年間の家賃収入を物件購入価格で割って求める投資指標。
計算式:
「年間家賃収入 ÷ 購入価格 × 100(%)」
経費や空室リスクなどを含まない「見かけの利回り」であり、実際の手取りを反映した「実質利回り」と混同しないよう注意。投資判断の初期段階での目安として用いられる。
分電盤
ぶんでんばん
建物内に引き込んだ電気を各部屋や機器に配電するための装置。一般家庭用では、メインブレーカー、漏電ブレーカー、個別ブレーカーなどが備わっている。
防水工事
ぼうすいこうじ
屋上・バルコニー・外壁などに対して行う雨水の浸入を防ぐ工事。ウレタン塗膜防水・シート防水・アスファルト防水など多様な工法がある。劣化すると漏水・カビ・構造部腐食の原因となるため、周期的な施工が推奨される。
防犯カメラ
ぼうはんかめら
エントランスや駐車場、共用廊下などに設置され、犯罪抑止やトラブル防止に役立つ設備。録画機能付きの高解像度カメラや、スマホと連動できるシステムも増えている。入居者の安心感を高め、入居率アップにもつながる。設置・更新には費用がかかるが、防犯設備費として共益費に含めるケースもある。
保証会社
ほしょうがいしゃ
借主が家賃を滞納した場合、オーナーに立て替え払いを行い、その後借主に請求を行う会社。入居審査、緊急連絡先の確認、与信管理などを担い、賃貸取引におけるリスク軽減に欠かせない存在。個人保証人の代替手段としても普及しており、契約更新時に更新料がかかることが多い。保証内容には範囲の違いがあるため、契約時の確認が必須。
ま行
間取り
まどり
住宅の部屋数や配置、広さ、用途などを図面や記号で示したもの(例:1K、2LDKなど)。間取りの表示には、居室の数とDK・LDK(ダイニング・リビング・キッチン)の広さが反映される。ターゲット層(単身・ファミリー・高齢者)によって求められる間取りが異なり、物件の競争力を左右する重要要素。図面上だけでなく、動線や収納力、家具の配置しやすさなども実用性の観点から評価される。
未納賃料
みのうちんりょう
借主が支払期限までに納めていない家賃。長期化すれば債権回収の難易度が上がり、法的手続き(催告、契約解除、明渡訴訟)に発展する場合もある。早期発見と対応が重要で、保証会社の利用や、口座引落・自動送金の仕組みにより未納防止が図られる。督促の際には、内容証明郵便や記録の残る方法が推奨される。
名義変更
めいぎへんこう
契約名義人(借主)が変更となる手続き。転勤・離婚・死亡などの理由で実施されることが多い。名義人の変更には、再契約や再審査やそれに伴う費用が必要となるケースもあるため、事前の確認と合意が必要。無断での名義貸しは契約違反となり、解除事由に該当する可能性がある。
免責事項
めんせきじこう
貸主または管理者が一定の責任を負わないと明記する条項。例えば、「共用部での盗難について責任を負いません」など。ただし、賃貸借契約における免責には限界があり、借主の生命・財産に重大な影響を及ぼすような部分(建物の安全性、衛生状態など)については、完全に責任を免れることはできない。契約書作成時には、消費者契約法・借地借家法との整合性が求められる。
メンテナンス
めんてなんす
建物および設備の点検・清掃・修理・交換などの保守業務全般を指す総称。日常的な維持管理と、経年劣化に対応する予防保全的な作業が含まれる。対応の質や頻度が、建物の資産価値や入居者の満足度に大きく影響する。
や行
家賃保証
やちんほしょう
借主が家賃を滞納した際に、保証会社がオーナーへ立て替え払いをする仕組み。保証料は借主が負担するのが一般的で、契約時に一定の初回保証料(例:賃料の50%)と年額更新料がかかる。家賃保証により、オーナーの収益の安定性が高まり、保証人不要での契約も可能になる。保証の範囲や免責条件は保証会社によって異なるため、契約内容の確認が不可欠。
床下点検口
ゆかしたてんけんこう
キッチンや洗面所の床に設置され、配管や基礎の点検・修理を行うための開口部。給排水トラブルや白アリ被害の早期発見に役立つ。定期的な点検が義務付けられる建物もあり、修繕対応のしやすさにも関わる設備。劣化が進むとカビや悪臭の原因となるため、長期入居者がいる物件では特に管理が重要。
養生
ようじょう
工事や清掃、引越しなどの際に、建物の床・壁・共用部などを傷つけないよう保護する措置。ダンボール、クッションマット、テープなどを使って行う。共用部の破損は管理会社や施工業者の責任になることもあるため、事前の養生計画と記録が重要。引越し時のトラブル防止にも直結する。
浴室乾燥機
よくしつかんそうき
浴室に設置され、洗濯物の乾燥、カビ予防、暖房・涼風など多機能に活用される設備。都市部や共働き世帯に人気があり、入居率に直結することもある。電気式とガス式があり、ランニングコストや乾燥スピードに差がある。設置後のメンテナンスやフィルター清掃など、設備の維持管理にも注意が必要。
ら行
LAN設備
らんせつび
建物内でパソコンやスマート家電をインターネットに接続するためのローカルエリアネットワーク(LAN:Local Area Network)設備。集合住宅では共用部に光回線を引き込み、各戸まで有線または無線(Wi-Fi)で接続する形式が主流。
礼金
れいきん
契約時に借主から貸主に支払われる、返還義務のない一時金。元来は「貸してくれてありがとう」の意味合いがあり、敷引きが通例であった関西圏ではあまり見られなかったが今では全国的に設定されている。地域によってはゼロ礼金物件も増えており、礼金の有無や金額が入居希望者の検討材料となることもある。物件価値やエリアによって相場が異なるため、募集時には相場調査が重要。
連帯保証人
れんたいほしょうにん
借主が家賃を支払えない場合、代わりに支払う義務を負う人物。通常の保証人と異なり、貸主はまず借主ではなく連帯保証人に請求できるため、責任が重い。保証会社を利用する場合は不要とされることもあるが、審査の補強材料として求められることもある。連帯保証人になる際には、十分な理解と同意が必要で、トラブルの元にもなりやすい。
ローン残債
ろーんざんさい
賃貸物件を購入した際の住宅ローンなどの借入金の、未返済分。売却や建替えを検討する際にはこの残債が影響を及ぼし、金融機関との交渉や査定価格次第では「オーバーローン(売却価格より残債が多い)」となるケースも。オーナーの資金計画や物件運営戦略に直結するため、適切な返済計画が必要。
わ行
ワンルーム
わんるーむ
キッチンや居室、収納などが1つの空間に収まった間取りのこと。単身者向け物件として人気があり、都市部では供給が多い。家賃設定や設備仕様によって差別化が可能で、学生・若年社会人・外国人など幅広い層がターゲット。管理上は、回転率が高い分、原状回復や募集手続きの頻度が上がる点に留意が必要。