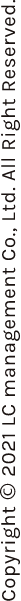EVICTION
アパート・マンションから立ち退きしてもらうために必須な「正当事由」とは?
立ち退きの正当事由とは?
賃貸物件のオーナーが入居者に立ち退きを求める際、法律上必要とされるのが「正当事由」です。これは、賃貸人が正当かつ合理的な理由を持って立ち退きを求めることを指し、正当事由がなければ入居者に対する立ち退き請求は認められません。
多くの方が、「賃貸人だから自由に立ち退きを求められる」と考えがちですが、実際には法律で厳しく制限されています。正当事由が認められるには、いくつかの要素を総合的に判断する必要があります。
そこで本ページでは、立ち退きの正当事由について、借地借家法の規定や判例を交えて分かりやすく解説します。
まずは、正当事由が認められるための具体的な要素について見ていきましょう。
正当事由を認められる5つの要素
では、この正当事由が認められるかどうかは、具体的にどのように判断されるのでしょうか。実際のところ、借地借家法第28条では、正当事由を判断する際に考慮すべき5つの要素が規定されています。
具体的には、以下の5つのポイントです。
-
賃貸人と賃借人の建物使用に関する必要性
-
建物の賃貸借におけるこれまでの経過
-
建物の使用状況
-
建物の現在の状態
-
立退料の提示
賃貸人と賃借人の建物使用を必要とする事情
賃貸人が自ら建物を使用する必要がある場合や、賃借人が建物を使用する理由が薄い場合には、正当事由として認められる可能性があります。
例えば、オーナーが高齢の家族と同居するために、自分の所有する物件に住む必要が生じたケースでは、この事情が考慮されることがあります。
建物の賃貸借に関する従前の経過
また、賃貸借契約の期間や過去の契約更新の履歴も、正当事由の判断材料となります。
具体的には、賃貸借契約が結ばれてから現在までの期間の長さ、賃料の支払い状況、契約内容やその更新の有無などが考慮されます。
ただし、長期的な契約であっても、オーナー側の事情が変わり、立ち退きが求められることがあります。
建物の利用状況
次に、建物の利用目的やその実際の利用が、契約内容に違反している場合について考えてみましょう。これは、正当事由の一部として認められる可能性があります。
例えば、多くの方が「契約を結んだら自由に使える」と考えがちですが、契約内容に反する利用は契約違反とされ、立ち退きを求める理由になり得ます。
建物の現況
さらに、建物の現況も正当事由の一部として重要です。例えば、建物が老朽化し、安全性が確保できない場合、立ち退きを求める理由となります。
具体的には、耐震基準を満たさない古い建物を解体するために立ち退きを求める場合などが該当します。
立退料の申し出
最後に、立退料の申し出についてです。立退料を提示することで、賃借人への補償を提供し、正当事由の一部として認められることがあります。
ただし、「立退料を払えば必ず立ち退きが認められる」と思う方もいるかもしれませんが、立退料はあくまで正当事由の一つに過ぎず、他の要素も総合的に判断される必要があります。
オーナー様のお悩み
をお聞かせください
皆様のニーズに合わせたプランをご用意しています。
メールでのご相談!
不動産オーナ様専用お問い合わせはこちら【営業時間】10:00〜18:00(定休日: 年末年始)
立ち退きが認められる具体的な正当事由
ここまで、正当事由を構成する要素について説明しましたが、実際にどのような状況で正当事由が認められやすいのか、具体的な事例を見ていきましょう。
-
01
建物の老朽化
建物が老朽化し、居住に適さない状態になった場合には、立ち退きを求める正当事由として認められることがあります。
しかし、単に築年数が経っているだけでは十分ではなく、建物の倒壊や設備の故障といった具体的な危険性が確認される必要があります。また、建て替え計画の詳細やその実現可能性も重要な判断材料となります。
-
02
オーナーの自己使用の必要性
賃貸人が建物を自ら使用する必要がある場合(例えば、家族の居住スペースとして使用する場合)も、正当事由とされることがあります。
もっとも、賃貸人が自己使用を必要とする場合でも、その必要性は賃借人の建物使用の利益と比較して判断されるため、必ずしも強い理由と見なされるわけではありません。
たとえば、賃貸人に既に他の居住用物件がある場合や、自己使用の必要性が急を要しない場合などは、その必要性が高く評価されないことがあります。
-
03
入居者の賃料不払い
入居者が長期間にわたり賃料を支払わない場合、これは重大な契約違反とされ、正当事由として立ち退きを求めることができます。
ただし、賃料の不払いについては、その期間や金額、また不払いの理由など、個々の事情が考慮されます。
例えば、賃借人が経済的に困窮しており、その状況を賃貸人が把握していた場合には、直ちに立ち退きが認められるとは限りません。
-
04
入居者による契約違反行為
入居者が契約に違反する行為を行った場合、例えば無断での転貸や物件の不適切な使用など、正当事由として立ち退きを求めることができます。
ですが、契約違反の内容やその程度、またそれによって物件オーナーが受けた損害の大きさなどが、個別に評価されることになります。
このように、正当事由が認められるためには、様々な要素が考慮される必要があります。それでは次に、立退料と正当事由の関係について考えてみましょう。
オーナー様のお悩み
をお聞かせください
皆様のニーズに合わせたプランをご用意しています。
メールでのご相談!
不動産オーナ様専用お問い合わせはこちら【営業時間】10:00〜18:00(定休日: 年末年始)
立ち退き請求の手順と流れ
では、賃貸人が賃借人に立ち退きを求める際の具体的な手順と流れについてご説明します。
-
01
立ち退きを求める際の通知期間
賃貸人が正当な理由に基づいて立ち退きを求める場合、まず賃借人に対して一定の予告期間を設けた上で通知する必要があります。
借地借家法 28 条によると、土地の賃貸借については6か月前までに、建物の賃貸借については6か月から1年前までに通知する必要があります。この通知の目的は、賃借人に新居の確保など、立ち退きの準備を行う機会を提供することです。
-
02
立退料の交渉と合意形成
立ち退きの通知後、賃貸人と賃貸人の間で立退料やその他の条件に関する交渉が行われます。
前述のとおり、立退料の金額は正当事由の決定に影響を与えるため、賃貸人としては、立ち退きの理由の合理性に応じて適切な金額を提示することが求められます。
立退料だけでなく、原状回復の費用負担や立ち退き日の設定など、さまざまな問題について合意を得る必要があります。
これらの交渉は、賃貸人と賃借人の間の直接交渉で行われる場合もありますが、弁護士や不動産業者など、第三者を交えて行われる場合もあります。
-
03
任意の立ち退きに応じない場合の
明渡請求訴訟以上のような交渉を経ても、賃借人が任意の立ち退きに応じない場合は、賃貸人は裁判所に明渡請求訴訟を提起する可能性があります。この訴訟では、裁判所が賃貸人の立ち退きの正当性を判断します。
訴訟では、先述した正当事由の要素がすべて考慮されます。賃貸人の退去理由が正当であると認められれば、判決で賃借人に明渡しが命じられます。
このように、立ち退き請求には慎重な手順が求められます。最後に、立ち退きを進める際に賃貸人が留意すべきポイントを確認しましょう。
正当事由を巡るトラブルと
その対処法
立ち退き交渉は慎重に進める必要があります。トラブルを回避するため、以下のポイントを押さえておきましょう。
立ち退き交渉の進め方
-

01
事前準備
借主の生活状況や権利を把握し、立ち退き料を検討する
-

02
事前準備
・口頭または書面で立ち退きの意向を伝える
・借主の事情をヒアリングし、相手の意向を確認
・立ち退き料の提示や補償内容を説明し、合意を目指す -

03
スムーズな進め方のコツ
誠実な態度で話し合いを進め、感情的な対立を避ける
正当事由が認められない場合の対応策
正当事由が不十分で、立ち退き請求が認められない場合、以下の方法を検討できます。
-

01
立ち退き料を増額する
補償額を増やし、借主にとって魅力的な提案をする
-
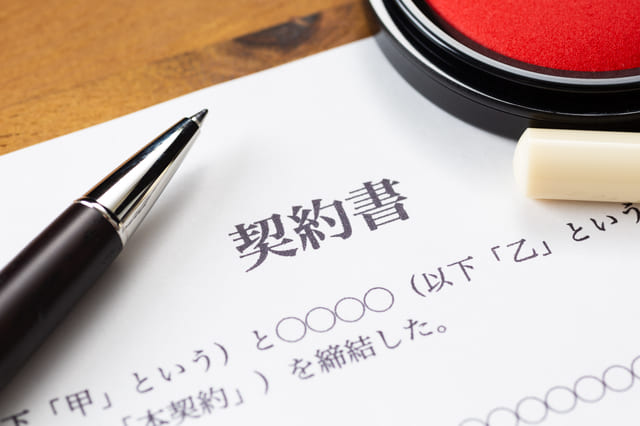
02
契約期間満了を待つ
定期借家契約であれば、契約満了時に終了できる
-

03
第三者を介して交渉する
弁護士や不動産会社を通じて交渉を進める
専門家への相談の重要性
立ち退き問題は法律的な知識が必要なため、専門家のサポートを受けることが重要です。
-

01
弁護士に相談するメリット
・正当事由の有無を判断し、適切な法的対応を助言してくれる
・借主とのトラブルを未然に防ぐための交渉を代行してくれる -

02
不動産業者に依頼するメリット
・借主との交渉を円滑に進めるための仲介役を担う
・立ち退き後の新しい入居者募集をサポート
正当事由が
認められなかった場合の選択肢
正当事由が認められない場合でも、貸主としてできる対応策はいくつかあります。裁判に進むのか、
それとも和解交渉を試みるのか、それぞれの選択肢を理解したうえで、適切な対応を検討しましょう。

裁判で争う場合
裁判で争う方法は、正当事由の有無を司法に委ね、法的に借主に退去を求める方法です。メリットは、適正な判断が下される点ですが、デメリットとしては裁判に長期間かかり、弁護士費用などのコストが発生すること、また関係が悪化する可能性があります。
和解交渉の場合は、裁判ではなく借主との話し合いで解決を目指します。メリットは、時間と費用を抑えられ、関係を円満に保ちやすい点です。しかし、借主が納得しない場合は交渉が長引き、立ち退き料を増額する必要がある場合もあります。

再交渉のポイントと注意点
再交渉で裁判を避けるためには、借主が納得しやすい条件を提示することが重要です。具体的には、現在より好条件の物件を提供したり、立ち退き料の増額を検討したりします。
また、借主に代替住居を提案し、引っ越し費用や家具移動などのサポートを提供すると交渉が進みやすくなります。さらに、口約束ではなく合意書を交わし、退去日や補償内容を明確にすることで、トラブルを防ぎ円滑に進めることができます。

不動産業者や弁護士に
相談するべきタイミング
借主との立ち退き問題では、弁護士と不動産業者のサポートが有効です。弁護士に相談すべきタイミングは、借主が交渉に応じず立ち退きを拒否する場合や、裁判を検討する場合です。感情的な対立が起きた場合も、弁護士が法律に基づいて解決をサポートします。不動産業者には、立ち退き交渉の代行や、借主へのスムーズな提案を依頼したい場合に相談すべきです。また、代替物件の紹介や貸主側の負担軽減も行えるため、交渉を円滑に進めるためのアドバイスを受けることができます。
賃貸人が立ち退きを進める際に
重要なポイント
賃貸人が立ち退きをスムーズに行うためには、次のことに注意してください。

早めの立ち退き請求と十分な交渉期間の確保
立ち退きが必要になることが予想される場合は、できるだけ早く賃借人に通知し、交渉を開始することが重要です。
法定の予告期間よりも余裕を持って通知することで、賃借人の立ち退きの準備に配慮しながら、合意形成のための十分な交渉期間を確保できます。

代替物件のあっせんなど賃借人への配慮
賃貸人は、立ち退きに伴う賃借人の負担を軽減するために、新しい物件のあっせんを行うことも効果的です。これにより、賃借人が新居を見つけるのに役立ちやすくなります。
また、引っ越し費用の負担や一時的な家賃減額など、賃借人の事情に応じた柔軟な対応を提供することもできます。

適切な立退料の提示
繰り返しになりますが、立退料の金額設定は、正当事由の補完として重要です。
賃貸人は、立ち退きの理由の合理性や、賃借人の不利益の程度などを考慮しながら、適切な金額を提示する必要があります。
ただし、あまりに高額な立退料を提示すると、賃借人の不信感を招く恐れもあります。したがって、賃借人の理解と協力を得ながら、誠実な交渉を進めていくことが重要です。
正当事由に関する
よくある質問
-
正当事由とは何ですか?
正当事由とは、契約や法的手続きの履行を拒否したり、遅延したりする際に認められる合理的な理由です。通常、法的な義務や契約を遵守する必要がありますが、何らかの不可抗力的な事情や正当な理由があれば免責されることがあります。
-
どんな状況で正当事由が認められますか?
天災や事故、病気など予見できない事情や、他の契約者による違反などが原因で履行が困難な場合に正当事由として認められることがあります。
-
正当事由が認められない場合はどうなりますか?
正当事由が認められない場合、その契約や義務の不履行に対して責任を問われ、損害賠償や契約解除などの法的措置を取られる可能性があります。
-
どんな場合に正当事由として認められるか、具体例を教えてください。
自然災害(地震、台風など)、火災、事故や病気、政府の規制変更、不可抗力な交通渋滞など、契約の履行を妨げる外部的な要因が正当事由として認められることがあります。
-
正当事由を証明する必要はありますか?
はい、正当事由を主張する場合には、その事由を証明する必要があります。例えば、病気の場合は医師の診断書、事故の場合は警察の報告書など、具体的な証拠が求められます。
-
病気の場合、どの程度の症状で正当事由が認められるのでしょうか?
病気が契約履行を妨げる程度であることが重要です。たとえば、入院を要するような重大な病気や長期的な療養を要する状態の場合に、正当事由として認められることが一般的です。
-
病気の場合、どの程度の症状で正当事由が認められるのでしょうか?
病気が契約履行を妨げる程度であることが重要です。たとえば、入院を要するような重大な病気や長期的な療養を要する状態の場合に、正当事由として認められることが一般的です。
-
もし正当事由が一度認められた場合、その後はどうなりますか?
一度認められた正当事由は、履行義務の免除や延長などを正当化する場合があります。ただし、その後も状況が改善しない場合、契約の解除や再度の履行を求められることがあります。
-
契約の履行が遅れる場合、正当事由があれば延長しても問題ないですか?
正当事由がある場合、履行期限の延長は認められることがありますが、延長される期間が合理的であることが必要です。相手方と合意することが重要です。
-
正当事由が発生した場合、相手に通知する義務はありますか?
はい、正当事由が発生した場合、その事由を相手方に速やかに通知する義務があります。通知しないと、相手が不利益を被る場合があり、責任を問われる可能性もあります。
-
正当事由によって契約解除が認められた場合、相手に損害賠償を求められることはありますか?
正当事由が認められた場合でも、解除することで相手に損害を与える場合、損害賠償を求められることがあります。ただし、正当事由がある場合、賠償額が減額されることもあります。