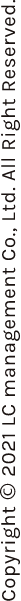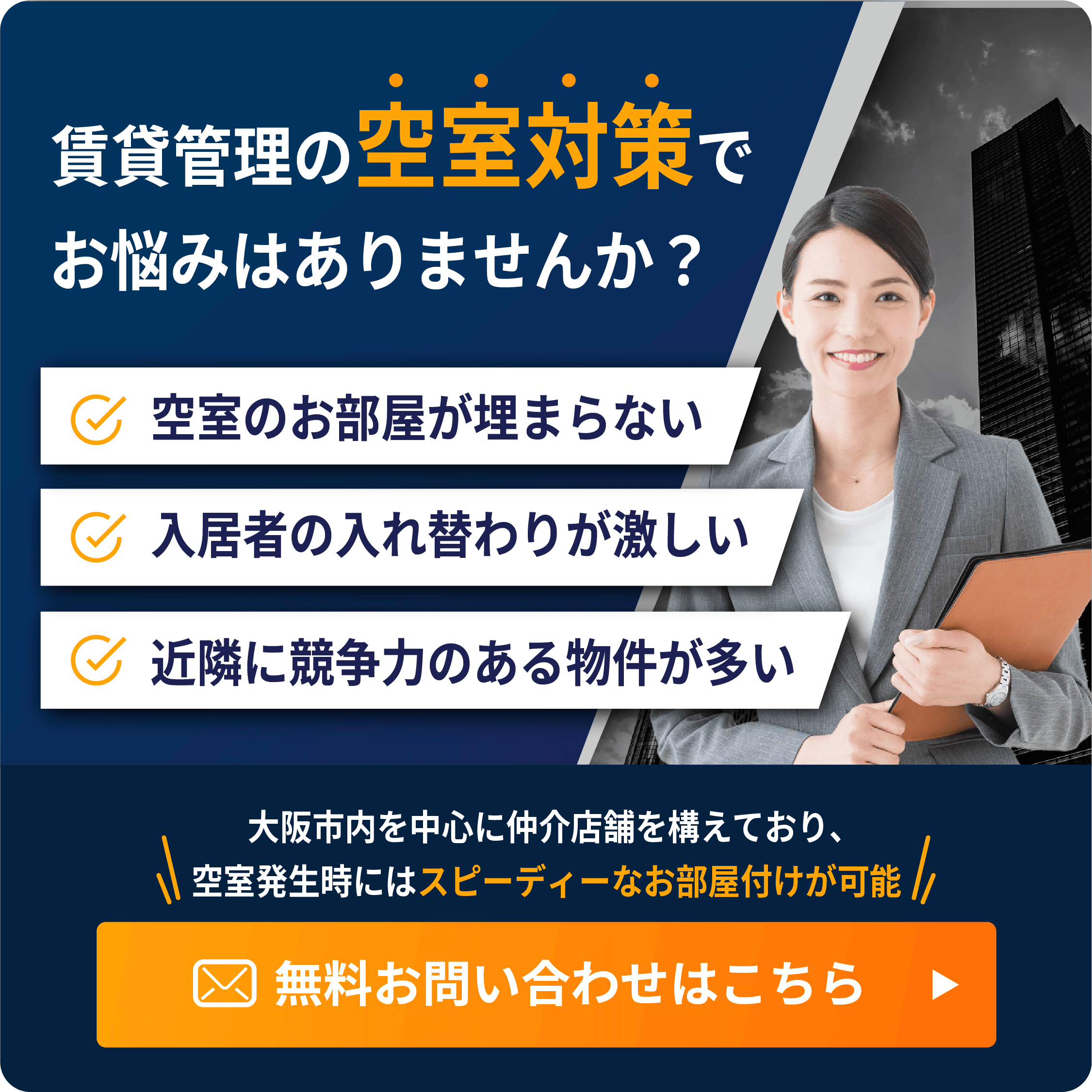日本は世界有数の地震多発国であり、過去には阪神・淡路大震災や東日本大震災といった甚大な被害をもたらした地震が発生しています。近年も南海トラフ地震や首都直下地震の発生が懸念され、賃貸物件を所有・運営するオーナーにとって、地震対策は決して他人事ではありません。実際に、地震による建物被害は入居者の安全を脅かすだけでなく、修繕費用の増大、資産価値の低下、最悪の場合は事業継続そのものを危うくします。
では、どうすれば地震に強い賃貸経営が実現できるのでしょうか?重要なのは、単なる応急処置ではなく、建物の構造的な耐震性を確保し、入居者とオーナー双方が安心して暮らし、経営できる環境を整えることです。
本記事では、耐震診断の受け方から具体的な補強工事、助成金の活用法、防災意識の向上まで、実践的かつ役立つ情報を章立てでわかりやすく解説します。

1. 現状の耐震診断を受ける
耐震性を高めるための最初のステップは、建物の現状を正確に把握することです。特に1981年以前に建てられた建物は現行の耐震基準と異なる旧耐震基準で設計されており、大きな地震に耐えられない可能性があります。自己判断せず、必ず専門家に耐震診断を依頼しましょう。
耐震診断の受診方法
- 診断業者の選定
耐震診断は建築士事務所や耐震診断士が行います。まずは自治体の公式サイトや建築士会のリストから信頼できる業者を探し、過去の実績や口コミも確認しましょう。
2.見積もりの取得
複数の業者に問い合わせ、診断内容、費用、所要日数の見積もりを取りましょう。診断費用は建物の規模や構造で異なります。自治体によっては助成金を利用できる場合があるので、あらかじめ確認するのがおすすめです。
3.診断の実施
業者が現地調査を行い、建物の図面を基に壁、柱、基礎部分などの強度や劣化状況を確認します。外観の目視調査だけでなく、必要に応じて詳細な測定や材料の試験が行われることもあります。
4.診断結果の説明を受ける
診断後は詳細な評価書が発行され、耐震性を数値(例:Is値)で示した結果が説明されます。このとき、オーナー自身も十分理解できるよう質問し、必要な補強内容や優先順位、概算費用を確認しておくことが大切です。
耐震診断は形式的な手続きではなく、建物の安全性を根本から見直す大事なステップです。この情報をもとに、今後の補強工事や資金計画を具体的に立てることが可能となります。
2. 耐震補強工事を行う
耐震診断の結果、補強が必要とされた場合は、早めに具体的な対策に着手しましょう。補強工事は建物の構造や劣化状況によって内容が異なるため、専門業者としっかり相談しながら計画を立てることが重要です。
構造による違いと補強方法
- 木造
日本の賃貸アパートで多い木造は、壁の強度不足や接合部の弱さが問題になりがちです。耐力壁の追加や筋交いの補強、金物補強が中心となります。
- 鉄骨造(S造)
鉄骨造は木造と比べると、耐震性能が高い場合が多いですが、接合部や錆び、部材の座屈(折れ曲がり)が弱点です。補強にはブレース(斜材)の追加や接合部の補強、耐火被覆の再施工などが検討されます。
- 鉄筋コンクリート造(RC造)
RC造は丈夫ですが、ひび割れやコンクリートの劣化、鉄筋の腐食が問題になることがあります。補強には炭素繊維シートの巻き立てや鉄板巻き立て、耐震壁の追加などの方法が用いられます。
補強工事の主な内容
- 壁の強化
耐力壁を追加したり、既存の壁を補強することで、横揺れに耐える力を高めます。木造の場合は合板を使う方法がよく用いられます。
- 柱・梁の補強
接合部の金物補強や、必要に応じて柱や梁そのものの補修・交換を行い、建物の骨組みを強化します。
- 基礎部分の補強
基礎が弱い場合は、コンクリートを増し打ちしたり、アンカーボルトを設置して地盤との連結を強めます。
- 屋根の軽量化
重い瓦屋根は地震時の揺れを増幅させるため、軽量の瓦や金属屋根に交換することで、負担を減らします。
工事の進め方と注意点
- 優先順位を決める
診断結果を基に、最もリスクの高い箇所から順に補強する方法を検討しましょう。予算や工事の都合に応じて、段階的に進めることも可能です。
2.費用の確認と資金計画
補強工事の費用は建物の規模、施工内容によって数十万から数百万円規模、さらにはそれ以上になることがあります。複数の施工業者から見積もりを取り、内容と費用を比較検討しましょう。助成金の活用も視野に入れ、資金計画を立てるのが賢明です。
3.入居者への配慮
工事中は騒音や一時的な立ち入り制限が発生する場合があります。事前に入居者へ丁寧に説明し、理解と協力を得ることが、トラブル防止のカギとなります。
補強工事は単なる修繕ではなく、物件の価値を守り、安全を確保するための長期的な投資です。信頼できる業者と連携し、しっかり計画を立てて進めましょう。
3. 室内や共用部分の安全対策
建物の補強が済んでも、室内や共用部分での対策が不十分だと、地震時に家具の転倒や設備の落下によるけがが発生する恐れがあります。ここでは簡単に始められる対策を紹介します。
室内の対策
- 家具の固定
タンス、食器棚、本棚などの大型家具は、専用の固定器具やL字金具で壁にしっかり固定しましょう。転倒防止ベルトや突っ張り棒も有効です。
- 家電製品の転倒・落下防止
テレビ、冷蔵庫、電子レンジなどの家電製品は、滑り止めシートや固定ベルトを活用し、揺れで移動・転倒しないようにします。
- 非常用品の備蓄
懐中電灯、乾電池、非常食、飲料水、簡易トイレなどの防災グッズを、各部屋ごとに備蓄することを入居者に推奨します。
共用部分の対策
- 棚や掲示板の固定
共用スペースに設置されている棚、掲示板、消火器ボックスなどが転倒・落下しないよう固定します。
- 照明器具や天井材の補強
地震の揺れで照明器具や天井材が落下しないように、定期点検を行い、必要に応じて補修・補強をします。
- 避難経路の安全確保
共用階段、廊下、非常口周辺に障害物がないかを定期的に確認し、避難経路を確保します。
入居者への案内・啓発
オーナーとして、入居者に防災意識を持ってもらうために、家具固定の案内チラシを配布したり、共用部に避難経路図を掲示することも効果的です。簡単な取り組みから始め、入居者と一緒に安全な住まいづくりを進めましょう。

4. 助成金の活用と防災意識向上
耐震診断や補強工事には多くの費用がかかりますが、国や自治体からの助成金・補助金を活用することで負担を減らせます。さらに、入居者と一緒に防災意識を高めることで、より安全な住環境をつくることができます。
助成金の活用方法
- 情報収集
まず、物件所在地の自治体の公式サイトや窓口で、耐震診断・補強工事に関する助成金制度を確認しましょう。制度は地域によって異なるため、最新情報をしっかり集めることが大切です。
2.申請準備
助成金を受けるには、申請条件を満たす必要があります。必要書類(診断結果、工事計画書、見積書など)を揃え、申請期限内に提出できるよう計画的に進めましょう。
3.スケジュール管理
助成金には予算枠があり、早めの申し込みが必要な場合もあります。申請から交付決定、工事実施までの流れを事前に把握し、無理のないスケジュールを立てましょう。
注意点
助成金は予算に限りがあり、申請が集中すると早期終了する場合があります。スケジュールをしっかり立て、必要に応じて早めに動き出すことが大事です。
助成金や補助金の活用は、オーナーにとって経済的負担を減らし、効率的に物件の耐震化を進めるための強力な武器です。地域の情報に常にアンテナを張り、チャンスを逃さないようにしましょう。
防災意識を高める取り組み
- 防災マニュアルの作成・配布
物件ごとの避難経路、非常口、連絡先などをまとめたマニュアルを作成し、入居者に配布することで防災意識を高めます。
- 防災訓練の実施
管理会社と連携し、年に1回程度の防災訓練を行うと、いざというときの避難がスムーズになります。
- 入居者とのコミュニケーション
日頃から入居者に防災の重要性を伝えることで、住民全体の防災力が向上します。掲示板やチラシ、定期的なメッセージ配信などを活用しましょう。
助成金の活用と防災意識の向上は、賃貸物件の安全性を高めるだけでなく、入居者からの信頼を得る大きな要素となります。オーナー自身が率先して行動することが、安心できる物件運営につながります。
まとめ
地震に強い賃貸経営を実現するためには、ハード面(建物の耐震性)とソフト面(入居者の防災意識)の両方をバランスよく整備することが不可欠です。具体的には、
- 定期的な耐震診断を受け、建物の現状を把握する
- 構造や状況に応じた補強工事を実施する
- 内装や家具、共用部分の転倒・落下防止を行う
- 助成金・補助金を活用して経済的負担を軽減する
- 入居者と協力して防災意識を高める
これらを着実に積み重ねることで、入居者が安心して暮らせる環境を提供し、オーナーとしても物件の資産価値を守り、安定した賃貸経営を続けることができます。
防災は「いつか起こるかもしれないこと」ではなく、「必ず備えておくべきこと」です。今すぐ行動を始め、あなたの物件を強く、信頼される賃貸物件へと育てていきましょう。
私どもLCマネジメントでは、不動産の専門家として管理委託から売却までオーナー様の大切な資産を有効に活用するための提案を行っております。
その他、事業内容・対応等のご相談、マンション管理業務に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。
.
.
株式会社LCマネジメント
大阪市中央区西心斎橋2丁目2番7号御堂筋ジュンアシダビル10階
電話 06-6211-0550